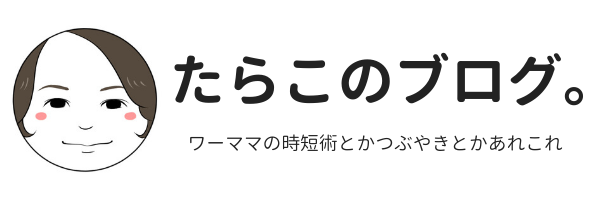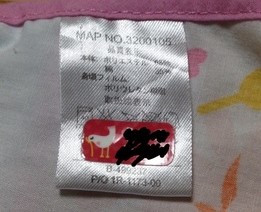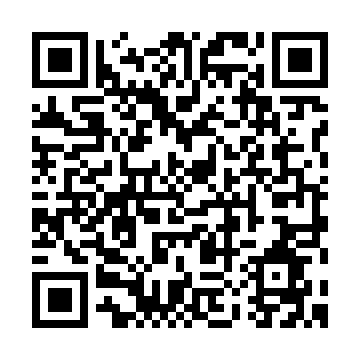うちのムスメは4月に小学校1年生になりましたが、入学と同時に休校になってしまいました。
勉強とは何かすらわからない状態で休校に入ったので、勉強習慣はほぼゼロ。しかもわが家は共働きで保育園出身なので(言い訳ですね)、ムスメはひらがなとカタカナがかろうじて読み書きできる程度です。書き順はめちゃめちゃです。
そんなわが家が試行錯誤しつつも続けているコロナ時代の新1年生の学習方法についてご紹介します。
メイン教材:スマイルゼミ
わが家の1年生のムスメのメイン教材はジャストシステムのスマイルゼミ。保育園時代からいろいろ試してみた結果、これがベストだと落ち着きました。
スマイルゼミの概要
専用タブレット端末に配信される教材をこなしていきます。一応毎日「今日のミッション」という課題が4アクティビティ分、課されます。1つのアクティビティはだいたい5~10分くらいでこなせるものです。
ただ、「今日のミッション」は過去にやったアクティビティもあえて復習のために課されるので、それがムスメにはあまり向いていないようです。
「今日のミッション」はあくまで提案なので、自分で好きなアクティビティを選んで学習することもできます。ムスメはこの方法でやることが多いです。
アクティビティを終了するとメダルをもらえます。
アクティビティを1日4つ終了し、タブレットを通して親に報告すると、獲得したメダルの数に応じた時間、ゲームをしたりマンガを読んだりできます。
スマイルゼミのいいところ
スマイルゼミの素晴らしい点は、タブレット端末の性能の良さです。
- 教材の品質が良い
- 手をついたままペンで字を書くことができる
- ゲームやマイキャラというご褒美をうまく使ってモチベーションを上げるのがうまい
まず教材の質の良さですが、とてもわかりやすいし、難易度もちょうどいいと感じます。
何よりすごいなと思うのが、子どもが書いた文字の入力と認識の機能です。
字を書くときって手の一部が紙(タブレット)につくじゃないですか。
普通のタブレットだと、そのついている手の一部にも反応してしまってうまくいかないのですが、スマイルゼミは手をつきながら自然に書いても、ペン先だけ反応するんです。
また、飽きっぽい子どもの勉強するモチベーションをうまく上げられるよう、よく考えられています。
その日の学習量に合わせて、ゲームができます。ムスメにはまだ難しいですが、歴史マンガも読めるようです。単純なゲームばかりですが、数十種類のアプリが入っていて、今のところ楽しみにしているようです。
ゲームとは別に、いつでもマイキャラという自分のアバターを作って着せ替えたりすることができ、これも楽しくやっているようです。月間の勉強量に応じて特別な衣装をもらえたりもします。
実はベネッセのチャレンジタッチもやってみたのですが、あちらはタブレット端末の性能が低すぎてお話になりません。学習のための動画視聴もタブレットの中央に小さく出てくるだけ。文字の練習も、手をついたままペンで書くことができないので書きづらい!絶対におすすめしません。
スマイルゼミの残念なところ
スマイルゼミの残念なところもいくつかあります。
- 1年生の教科は国語・算数・英語しかない
- 文字の練習は、きれいに書けても大きさなどがお手本とずれているとNGと判断される
- 英語は入会時期ではなく、学年によって内容が決まるので難易度が合わない
- 「今日のミッション」をカスタマイズできない
- ゲームアプリは漢字を多用していて1年生には難しい
個人的には許容範囲ですし、内容の品質がいいので続けていくつもりです。
サブ教材1:Think! Think!
シンクシンクは立体図形や論理思考に強くなる知育アプリです。会員2万人の学習塾、花まる学習会の幼児教育のノウハウを凝縮したパズルやゲームを、無料で楽しめます。
小さい子でもやる気が続き、自然と考える力が伸びていくように設計されているのがいいところ。無料だと1日10分程度までなのもちょうどいいです。

サブ教材2:スクラッチJr.
スクラッチJr.とは、5~7歳くらいの子ども向けのプログラミングアプリ。視覚的にもわかりやすいので、ひらがなが読めない子でも遊べます。
ほかにも幼児向けのプログラミングアプリにはビスケットというものがありますが、そちらは直感的にわかりづらいので、こちらのScratch Jr.がおすすめです。

「お勉強」よりも体験やSTEM教育を意識
上のサブ教材からもわかると思いますが、わが家ではSTEM教育(Science, Technology, Engineering and Mathematicsなどの教育分野)を意識しています。
なぜか?今のところ、ムスメはあまりお勉強が好きではないようす。運動もあまり得意ではなく、保育園時代から友達の中にも入らずに一人で遊んでいることが多い子でした。もしかしたらですが、小学校にうまくなじめないかもしれません。
そんなときに武器になるのはプログラミング力だったり、海外経験だったりすると思うのです。
思い込みで可能性を狭めないように気をつけないととは思いますが、いわゆる「お勉強のできる良い子」じゃなくても生きていけるように機会を与えてあげたいと思っています。
この本めっちゃ面白いです。子どものいるご両親に読んでほしい。